-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
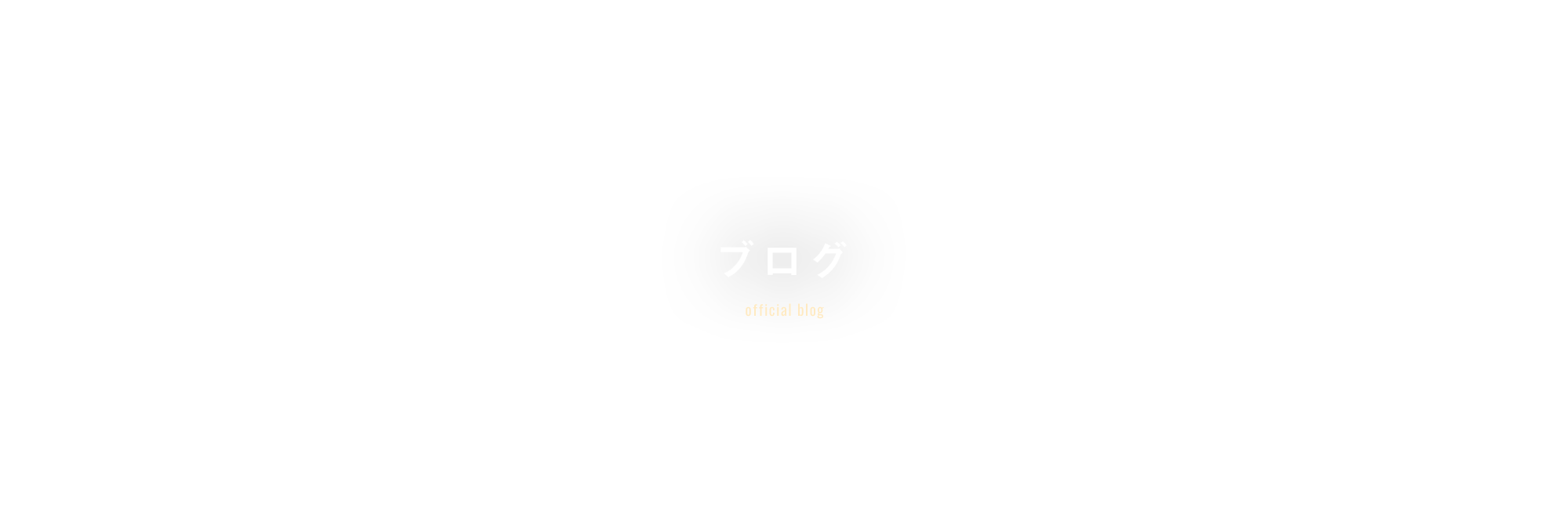
株式会社モリの更新担当の中西です
さて今回は
~注意~
ということで、現場のプロが実際に意識している「軽天工事の注意ポイント」を技術的・現場的視点から深掘りしてご紹介します。
軽天工事(軽量鉄骨下地工事)は、壁や天井の骨組みを正確につくる内装工事の要です。
その完成度が、仕上げの美しさ・建物の安全性・施工全体の効率に大きく影響するため、細部まで注意を払うことが求められる仕事です。
軽天は“下地”とはいえ、すべての仕上げの基準となる存在です。
壁がわずかに傾いて、クロス仕上げに波打ちが出る
天井が水平でないと照明器具の設置に影響
開口寸法ミスでドア枠や窓が入らない
墨出し段階での二重確認
レーザー墨出し機と下げ振りによる垂直・水平の確認
他職との打ち合わせによる寸法調整
「ミリ単位」の精度こそ、軽天工の誇りです。
軽量鉄骨(LGS)は軽量とはいえ、環境や扱い方によって精度に影響する素材です。
雨天時や湿気の多い現場での材料保管
床に直接置くと曲がり・汚れ・サビの原因に
投げ置きによる変形やバリ発生
乾燥した平らな場所にラック保管
現場搬入後すぐに仮組・仮置きで変形を防止
丁寧な運搬・保護具の使用
材料の精度を守ることが、施工の質につながります。
現場での“施工図”や“設計図”には、時に現実とのズレや解釈の余地がある場合もあります。
設計図と実寸が合わない(配管や梁の干渉)
高さ設定のズレ(天井高の変更・梁逃げ)
設計側の意図が不明瞭な記載
着工前に設計担当・監督と図面整合性の確認
現場実測による事前調整
柔軟な判断力と報告・相談の徹底
“現場目線”での判断力が、最終的な品質を左右します。
軽天工事は内装の初期工程であり、配線・配管・空調・断熱材など多くの業種との連携が必要です。
電気配線と干渉して吊りボルトが打てない
設備配管が軽天下地を貫通
他職との工程バッティングで手戻り
着工前ミーティングで工程と位置の共有
先行配管・配線とのタイミング調整
各業種との“現場レベル”でのコミュニケーション
「全体を見て動ける職人」が、現場に重宝されます。
軽天工事では、脚立・足場・天井内などの高所作業や火気使用が頻繁にあります。
吊りボルト作業中の墜落事故
グラインダー使用による火花トラブル
シャープエッジによる切創事故
墜落防止器具(安全帯・ヘルメット)の常時装着
火気使用時の監視・消火器配置
研磨・カット部の養生と周囲への注意喚起
「無事故」が職人としての信用に直結します。
軽天工事は、内装全体の精度・強度・美しさを決める「骨格づくりの仕事」。
その中で、わずかなズレ・不注意・認識不足が大きなトラブルにつながるため、“正確さと配慮”が何より重要です。
「見えないところにこそ、職人の力がある」。
この誇りを胸に、一つひとつの工程に責任を持つことで、より高品質な空間づくりが可能になります。
![]()
株式会社モリの更新担当の中西です
さて今回は
~軽天って?~
ということで、軽天工事における「軽天」とは何か?その素材・役割・施工技術までを、職人の目線から深く掘り下げてご紹介します。
建築現場で「軽天(けいてん)」という言葉を聞くと、「軽い天井のこと?」と誤解される方も少なくありません。
しかし、実はこの“軽天”こそが、現代建築における壁や天井の骨組みを支える縁の下の力持ちなのです。
軽天とは、**「軽量鉄骨天井下地」**の略で、天井や壁の内側に組まれる“骨組み”のことです。
主に**軽量形鋼(LGS:Light Gauge Steel)**と呼ばれる薄い鉄骨材を使用
C型や角形の断面で強度と軽量性を両立
石膏ボードなどの仕上材を貼り付けるための“下地”として使用
建物の美しさや強度の“土台”となる存在なのです。
かつては木材で組まれることが多かった内装下地も、今ではほとんどの現場で軽天に置き換えられています。
軽くて運搬・施工がしやすい
湿気や火に強く、変形しにくい
寸法精度が高く、大規模建築にも対応可
リサイクル性が高く、環境負荷が少ない
**強さと軽さ、合理性を兼ね備えた“現代の下地材”**として、建設現場に不可欠です。
軽天工事は、設計図面を読み解きながら、空間の中に正確な骨組みを組み上げるプロセスです。
**墨出し(基準線引き)**で正確な位置を確認
**ランナーとスタッド(支柱)**で壁の骨組みを形成
天井の高さに合わせて吊りボルトと野縁で天井下地を組む
最後にボード職が石膏ボードを張り付けて仕上げへ
「見えない部分」にこそ職人の精度と技術が問われる仕事です。
軽天工事は、設計に対する「正確な対応力」が求められる仕事です。
壁がまっすぐ立っていなければ、仕上がりがゆがむ
天井が水平でなければ照明のラインが崩れる
すべては“仕上げ職人の前段階”として責任重大
そのため、軽天職人には寸法精度・構造理解・施工スピードのすべてが求められます。
“空間を図面どおりに実現する”立体作業のプロフェッショナルなのです。
軽天が正確に組まれていることで、初めて以下のような空間が実現できます。
美しくフラットな天井
隙間なく閉じた間仕切り壁
防火性能や遮音性の高い空間設計
安全な配線・空調設備の収納スペース
つまり、軽天は「目には見えないが、空間の質を決める柱」。
**“表には出ないが、品質をつくる仕事”**なのです。
軽天は、ただの鉄骨ではありません。
それは**「空間の精度と安全を支える骨組み」であり、「建築の美しさの裏にある職人の手仕事」**です。
見えないところにこそ、本当の技術が宿る――
そんな信念で支えられているのが、軽天工事の世界です。
![]()